財務省が発表した「成長、人口・地域等」。
少し前に発表されたレポートですが、知っておかねばならない国の現状を改めておさえることができるので読んでみました。
けっこうゾクッとする内容です。
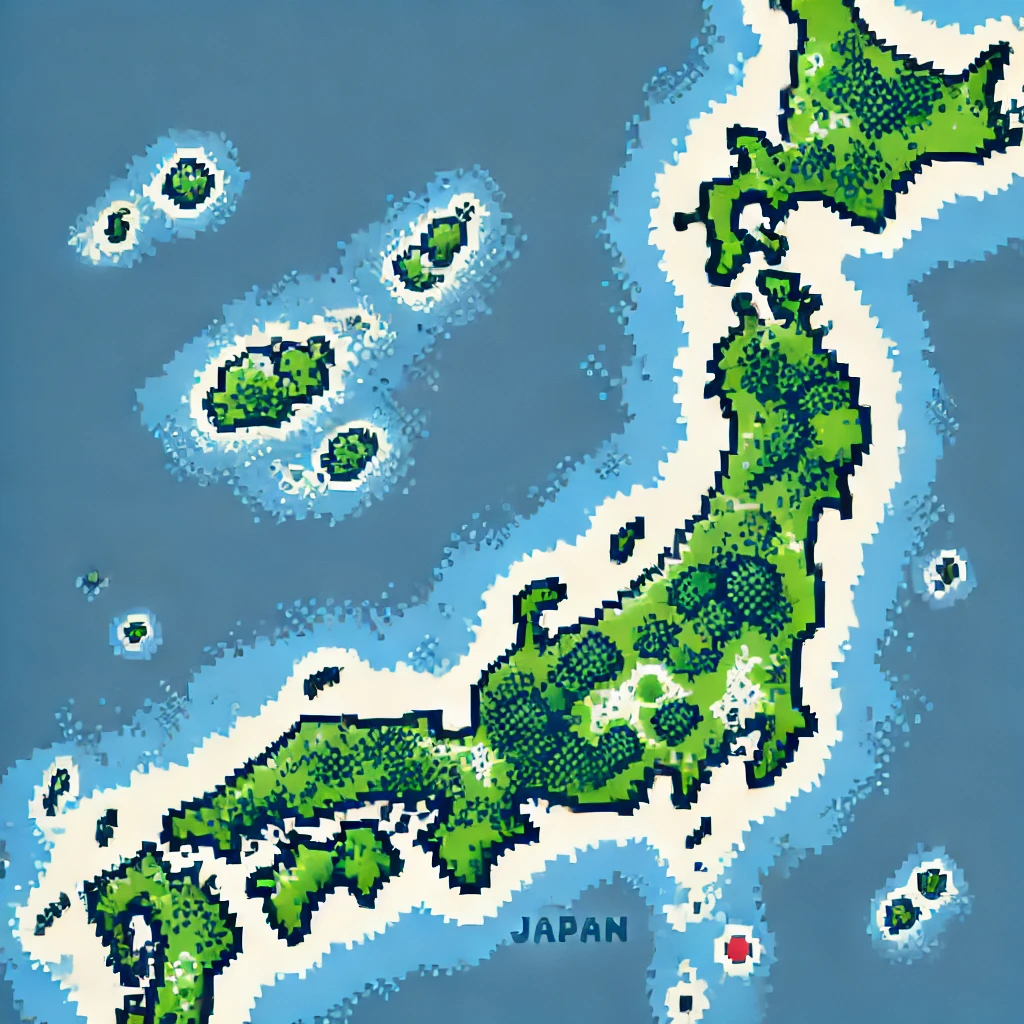
各配信サービスでもお聴きいただけます
※睡眠導入用じゃなければ1.5倍速がおすすめです!
自分でも「牛がしゃべってんのか?」と思うぐらい話し方がゆっくりです。
AIによる要約
このポッドキャストでは、財務省が発表した成長人口地域に関するレポートを基に、日本の現状や経済の課題が論じられています。特に労働市場の改革や2050年に向けた将来の人口動向に焦点を当て、スモールビジネスの視点から重要な問題が提起されています。このエピソードでは、地方自治体の効率化やデジタルトランスフォーメーションの必要性が語られ、さらに人口減少と東京一極集中による行政サービスの格差についても触れられています。
参照資料
文字起こしテキスト全文
このポッドキャストでは、スモールビジネスやその周辺のカルチャーについての話題をお届けしていきます。
再生ありがとうございます。
ウェブディレクションと音源制作を手掛けるシララ株式会社の伊東宏之です。
今日は財務省が出した「成長、人口・地域等」という、すごい硬い名前のレポートについてお話ししたいと思います。
スモールビジネスのオーナーの皆さんというのは、まさにこのレポートのタイトルにもなっているような、国の成長分野とか、あるいは人口地域を分解した結果の市場で戦っているということがほとんどですよね。
なので注目すべきレポートだと思うんですが、なかなかこういうのって読むのめんどくさい。
というわけで、おぼつかないところがありますが、私が皆さんに代わって、ごく簡単にサマリーをお話ししたいと思います。
まずこの資料の全体的なふわっとした感想を述べますと、ビジネスパーソンであれば、様々なニュースで既に概要を知っているようなことが並べられてはいるんですよね。
例えばリスキリングの話とかがこのレポートでも結構触れられているんですが、それを点ではなくて線や面として一気通貫で、日本の現状として再認識するのに優れたレポートだなと思いました。
このレポートは2024年4月に発表されたもので、3つの章に分かれています。
1章目が日本の現状と財政のあり方、2章目が成長等、3章目が人口地域ですね。
実は、ちょっとした前提情報として、一部のこのレポートのグラフに関して信憑性に疑義がSNS上とかで上がってはいるんですよね。
おそらく財務省という特別なポジションから発するレポートというのもその背景にあるのかもしれないですね。
ですので、そういった声があることも頭の片隅には置いておきつつも、とはいえ、国が発表している一次資料なので非常に興味深いですし、日本の現状を突きつけてくる資料であることには違いがないので、チェックしておいて損はないなと思いました。
で、全体の概要としてはですね、メッセージとしてはこういう感じです。
「財政赤字やばいよ、しかも経済成長してないよ、労働人口がめちゃくちゃ減ってるよ、だけどみんな東京ばっかり住みたがるよ」
こういう大問題を日本は抱えていますよという話なんですね。
それに対してこのレポートでは、EBPM、Evidence Based Policy Making、
エビデンスに基づく政策形成をしないといけないよというふうに強調されています。
これが抽象化した全体論です。
というわけで、第一章の「日本の現状と財政のあり方」についてお話ししたいと思います。
(響きが)硬いですね・・・。ここで述べられているのは政府債務残高、政府債務残高は1000兆円オーバーなんだけども、GDP、つまり国内総生産ですね、これは横ばいだと。
GDP比に対して250%も債務残高があるよということですね。
これまで財政の支出というのは景気対策をターゲットとして拡大してきたんだけども、その効果が不明確じゃないかというふうにこのレポートで述べられているわけですね。
なので先ほどのEBPM、エビデンスに基づく政策形成によって政策効果の厳格な評価が必要だと。
約5000の予算事業を徹底的に見直すべきで可視化しようよ!という主張がされているわけですね。
実際ですね、このレポートの発表の後にそれが実装されまして、「行政事業レビュー見える化サイト」というのが立ち上がっていますよね。
概要欄にURLを貼っておきます。これからこのサイトにもデータが溜まっていくんだろうなという感じなんですけれども、一国民としてこれはもうすごく良い動きだなと思いました。逆に言うと全然何かこういうのがなかったんですね。
あと、ふとした疑問なんですけれども、国会議員の方はどのぐらいこういうのを活用するんでしょうね。
議員さんってやっぱり質の良し悪しの差が結構激しいので、こういったことを全然知らない人もいそうだなと・・・いうふうに想像しました。
では第2章「成長等」です。ここで述べられていることは経済成長率が日本はもう1%台だよと。
それで生産年齢人口と働き手の人口がどえらく減っていくし、民間の投資も他の先進国と比べて鈍ってるし、やばいぞということが言われてるわけですよね。
そのために三位一体の労働市場改革というのが提唱されています。この三位一体の一つ目が、リスキリングですね。
これは当然その生産年齢人口、働き手が減っていくので、一人当たりの能力を上げて引いては生産性を上げなきゃいけないよねということですね。
そして2つ目。2つ目は実態に応じた職務級の導入ですね。
これどういうことかというと、例えば半導体とかDXとかAIの成長分野で、これまでの日本の製造業でずっと脈々と受け継がれてきた年功序列とか、
画一的な賃金体系だと絶対諸外国に勝てないよという話ですよね。それはそうですね。それだと優秀な人、正直やっぱりこのAIの分野とか来ないですからね。
3つ目がこれと完全に連動する話なのですが、成長分野への労働移動ですね。
労働移動ってすごい言葉ですね。つまりその分野に人が集まるようにしなきゃいけないよねということですね。
こういったことを前提として、例えば教育訓練給付の拡充でリスキリングを促進していくような制度改革だとか、あとはすでに半導体産業への支援といった具体例があるので、それが掲載されていました。
半導体への支援というのは対GDP比で今0.71%だそうで、これは実はアメリカやフランスの0.2%台よりも高いようですね。
あとは民間の投資が鈍っててやばいぞという件については、ODA、政府開発援助ですね。
これと紐付けてレポートの中で語られてはいるんですけれども、財務省と外務省の間での論点とかがずらずら書いてあって、
ややスモールビジネスは遠いかなと思ったので、ちょっとここは割愛したいと思います。
第3章「人口・地域」です。ここがやはりスモールビジネスと特に接点がある話題ではないかなと思います。
このレポートって全体的に将来の話、それが具体的にいうと2050年にフォーカスして触れられていることが多いんですよね。
2050年ってたった25年後です。すぐですよね。
だって当たり前の話ですけど、今から25年前って西暦2000年じゃないですか。そんな昔な感じしないですよね。
だから25年ってあっという間に経ってしまうんだなというところなんですけれども、
その頃に我々は当然生き残っていないといけないし、子どもたちが住む世界がひどいものになっていってはいけないですよね。
この2050年なんですけれども、この章で書かれているのは8割の地域で人口が30%以上減少する。
8割の地域で人口が30%以上減少する。
2割の地域が無居住化。2割の地域で誰もいなくなる。
道路とかのインフラの便益の指数というのも言及されているんですが、これが1.0を切ってしまう地域があるということなんですね。
つまり住民の数に対しての便益という数値だと思うんですけれども、
となるとインフラを今のように維持していくということが各自治体が行うという判断ができない場合もあり得ますよね。
このレポートの中でやはり能登の地震も引き合いに出されていて、そういったことと関連づけてコンパクトな街づくり、コンパクトシティと呼ばれているやつだと思うんですけれども、これが提唱されていました。
一つ我々スモールビジネスをやる上で考えなきゃいけないのは、僻地にいてもリモートでやれちゃう業種って結構多いじゃないですか。
だから田舎に移住したという人もいますよね。
ただ現時点ではもちろん大丈夫なんだけれども、いわゆる僻地では、
たった15年とか25年経た先でインフラが維持できない可能性があるということですよね。
これはもう事業をする上で結構大事な検討ポイントになってくるかと思います。
全国で生産年齢人口も25%減るそうなんですね。
なので特に四大都市以外の地域では自治体職員自体が確保できないという話がここで書かれていました。
恐ろしいですね。
それで自治体の効率化、DX化が急務だというふうに主張されています。
先ほどの前の章でも、DX分野への人材確保が非常に重要だというふうに書かれていたこととちょっと繋がりますよね。
もしかしたらこの辺りに特に小規模な自治体であればあるほど、
スモールビジネス側から見れば何か食い込んで支援するというチャンスがあるのかもしれません。
それで詳細は割愛したいんですけれども、
学校の先生の給与のこととか働き方とか人材不足の深刻さについても言及されているので、そのあたりにご興味のある方はぜひレポートを読んでみていただければと思います。
あとはですね、これは言わずもがなな話で、税収も人の移動、人口も東京一極集中で、
そうなってくると行政サービスに関してがそれ以外の地域と格差がすごいよというふうに述べられていますね。
例えば首都圏内ですら東京と隣県の間で子育て支援とかで格差ができていると、
つまり東京が手厚いということなんですけれども、
これを是正するのは少子化対策としても重要だというふうに述べられていました。
このレポートに直接的には書かれていないんですけれども、
人口の転入超過ですね。毎年1月に昨年分のデータがニュースになっていると思うんですけれども、
この間も1月のニュースを見ていたら基本的に明らかな転入超過は首都圏と、あと4大都市、大阪、名古屋、福岡だけのようなんですよね。
なのであくまで経済的なスモールビジネスという意味での部分で考えると、そのいずれかのエリアに、べつに住まないとしても、何かしらそことの繋がりをしっかり確保しておくというのが、どうしても生き残りの優先的な選択肢になってくるのかなと思います。
個人的にはそうですね、ちょっと逆張りして北海道で札幌とかの都市に特化して活動するとかも十分面白いなと思うんですけれどもね。
いずれにしても人がいる、いないの勾配がこれからより急峻になっていきますよということですね、この25年で。
しかも25年後に急に発生するわけではなくて、もう始まっているという怖さですよね。
それがやっぱり結構このレポートでよくわかりました。
あと今回のレポートで成長分野への労働移動ということも明示しているわけなので、
分野への見極めというのですね、この2、3年でも意識して展開していかなきゃいけないなと思いました。
というわけで、ちょっとヒヤッとザワッとするような話題で申し訳ないんですけれども、概要をご説明しました。
これ毎年4月に出してほしい資料ですよね。
では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
このチャンネルは大体月1回、2ヶ月に1回ぐらいの時もあるんですけれども、そのぐらいの配信頻度で追いつくのがすごい簡単なので、よろしければフォローをお願いいたします。

